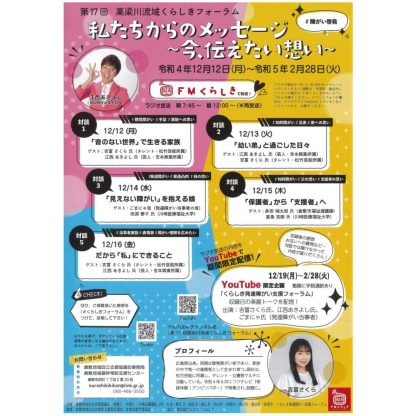凸凹お便り編集部企画 にじいろさぽーと代表阿部さん&訪問カットしの:佐々木さんスペシャルインタビュー③~倉敷発達障がい者支援センター~

【第三部 情報発信とサポートカードについて】
発活動のSNS発信について、阿部さんもおっしゃってたんですけれど、ご自身の記録として始めたものが積み重なって、周りの周知へつながっていく。その発信の仕方もすごく気を遣うことがあると思うのですが…阿部さんもありますか?発信をするときのマイルールのようなものは。
a:マイルールですか・・。でも私愚痴とかも結構発信してるので(笑)…何なら特にマイルール…というのはないんですが、私、サポートカードの普及啓発活動を行っておりまして、「サポートカード」について知らない方もまだまだたくさんやっぱりいらっしゃるので、どこかの講演でお話をさせてもらったりとか、具体的にカードを作ったりした場合には(SNSに投稿するにあたって)細かくその載せるようにはしていますね。「サポートカードっていうのは…」という感じで。
この前も長男のランドセルに移動ポケットをつけたことを載せました。本人の写真についてはいろんな方に見てもらうようにしているから気にしながら。でもこれ実際あったら便利だからというものを載せたりはしてます。特別あまり(マイルールとか)気にはしていないかも。
ハンドメイドについてもごっちゃになっていろいろ載せてるんで(笑)
しのさんほどのきちっとした感じは全然なくって…しのさんのSNSを見させていただいたんですが、訪問カットは何かしら聞いたことがあったんですけれど詳しいことは聞いたことがなくて知らなかったのでとても勉強になりました。
自分の息子も小っちゃい時興味を引くように車の乗り物がある散髪屋さんに連れて行ったりとかしてまして、でももうほんとに大変でした。だから息子の場合はずっと小っちゃい時から私が自分でカットをしていて、羊の毛刈りのように刈ってて(笑)、アイスクリームを与えてみたりとかいろいろしながら工夫していました。息子は母さんが切ってくれるっていうので慣れてくれたからよかったけど、特に敏感なお子さんだとしのさんのような方がいてくださったら親御さんも安心できると思います。カット見てても私凄いこのカットの仕方好きだなって思いました。
佐:いやいやいやいや…(照)

a:今日載せられてたのも(取材時7/22現在)
子供さんのね、ああこれいいなと。
佐:長めが好きな子で、5か月ぶりだったので顎ラインになってました。可愛いお子さんです。はい。
発:いいですよね、当たり前の基準にもっていくというよりその人が一番いいところにもっていくっていう…器用なお母さん達だったらご自身でもできるんでしょうけども…。
佐:保護者の方にも、やっぱり大きくなってから限界があるって言われるんですよ。よく言われるのは歯医者と美容室は「小さい時から将来的には現場に行けるように」と先生に言われてって。
小さいうちから慣らす、家ではなくっていう。家でもいいけどやっぱり子供って大きくなるし親も年を取ってくる、となると限界が来るんですよね。今はいいんですよ。訪問カットじゃなくてもお子さんが寝てる間にお母さんがこっそり半分切って、また次の日に切ってっていろいろできる。
やっぱり大きくなるとそれが難しくなりますよね。そういうお声はうかがうことがあるかなあ。
発:阿部さんのお話にもつながるんですが、例えば美容室に行くことにチャレンジしようとしている方にももしかしたらサポートカードって使えるかもしれないですよね。その場面では「こういう風にしてもらえると快適」、とか「落ち着いて待てます」というような意思表示・取説の道具しても使えるような…
a:サポートカードでなく「ヘルプカード」というものがあるっていうのは知ってたんですけれども、サポートカードを作ろうと思ったのが、保育園から小学校に上がる親の目が行き届かなくなる子供がちょっと自立するいう状態の中で、果たしてヘルプカードを持ってる子がどれだけいるかなと思って。

まずヘルプカードも普及し切れていないし、他のお子さんがへルプカードを見てどう思うかっていう。
大人の方は支援の必要な方が持つカードっていうことはわかると思うんですけど、他のお子さんから見て多数派の子が持ってないようなものを持っているっていうところで、からかいとかそういう対象になったら怖いなっていうところがあって。そこから色々検索をしていると、他の県では「サポートカード」っていう物があるっていうところまで行きつきました。
とりあえずこう、かわいらしく、パッと見て気にならない感じで持てるものというところでサポートカードを考えたので、なんかその美容室なり歯医者さんなりっていうところでも小さい子用の感じで作ってます。文章とか短めにしてわかりやすく書いてたら見る方もわかりやすいでしょうし。
長男も小学校に行った時にまず表を先生が見て、で、中は何書いてるんだろう?って見てくださったらしくって。そしたらチックの種類がいろいろ書いてあって(私も調べて暴言とかもチックの一種なんだなっていうことを初めて知ったので)という流れで見てもらえました。
学童指導員の先生も「これを見て初めて知りました」って方ももちろんいらっしゃったので、あってよかったなと思います。
発:本を持ってこられるより、すっと入ってきますし、ぶらぶらと何か面白そうなものをぶら下げていたら見たくなりますよね(笑)。
佐:そうですよね。気になるし来客された方が持ってこられたら便利。
ここで対談の記録をサポートくださっていたセンターの利用者さん(青年期の当事者さん)も話題に参加・・

利:多くの方だと、どの美容院に行く?から始まるじゃないですか。でも私たちの場合ってまず何したらいいんだろう、どこに頼んだら切ってもらえるんだろうっていうところから始まると思います。段階はいろいろにしても選択肢が増えるのはすごくいいなあと。
a:障がいがあるからという理由でかかりつけ医に行ってくださいって受診を断られたこともあるし、予測のつかない処置を次々に進められて本人がトラウマになってしまって、もう拒否するような感じになったりとか、いろいろ転々としてますが理解のある歯医者さんを探さなきゃって思っているところです。
発:それこそ何を怖がっていて、何が嫌だったかって伝えてくれるのは数年後だったりして…
利:私もかかりつけにしてた歯科があったんですけど疎遠になってしまって、4年間行けなくて。でも身近な家族に「私はこれが嫌だからこうしてほしい」って言えるようになってからトントンと話が進みました。やっぱり自分で自分の苦手なところ嫌なところを言えるようになるっていうのがやっぱり大きな分岐点だったかなっていう感じします。受け入れてもらえたので自分自身も楽になりました。
発:それを伺うとお母さんが一人で「ああなのかな?こうなのかな?」って思うだけの時間って、とってもしんどいですね…。
a:小学校入ってぽろっと自分の気持ちをたまに言ってくれたりするときがあって、ああこういうことだったんだ。なるほどってうれしくなりますけど、それでもまだ3年生なのでたまにですね。
発:言葉だけでなくてその子なりの伝え方えをキャッチしたいですよね。いろんなことを思っているかも…
a:それを聞いてたら、うちは支援級の先生とか学童の支援員の先生とかが知ろうとしてくれてるなと感じます。サポートカードとか本とか出した経緯もあったり、普段から細かく申し訳ないくらいに情報共有の話をするので、先生からも「こういう状況でした」、「こういう気持ちだったみたいです」、と言ってくれるので自然と先生方も長男の今のこの表情とかはこういう気持ちなんだなっていうのを知ろうとしてくださっているからなんだろうなと感じたり…そういう人が増えたらね。